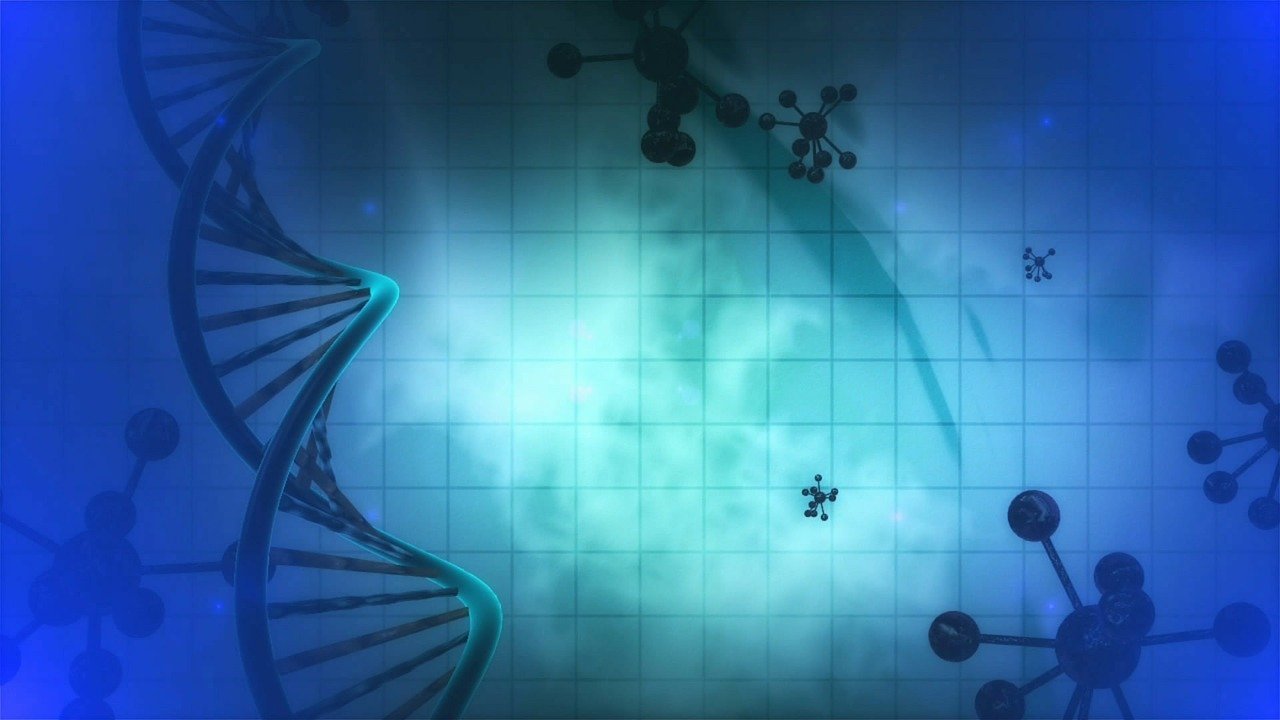同性間の性行動は,様々な動物種の間で見られるが,このような行動が複数の種で発達させられてき進化的理由は何なのかということについて科学者たちは頭を悩ませてきた。先週Nature Ecology and Evolutionで発表された研究は,この問い自体がそもそも間違いであるという可能性を議論している。
これまでの見方は,異性間の性行動が基本として存在し,その中で同性間の性行動が進化したということを前提にしていた。しかし,新たな研究の著者らは,同性間の性行動こそ動物の性行動の起源であり,その関係は逆なのであるという仮説を提唱している。
彼らの仮説では,初期の有性生殖をする生物は,性に関係なく,とにかく出くわす個体と性行動を行っていたということを主張する。これは,カタツムリやウニのような両性生物で今でも行われていることである。生殖のターゲットとして認識することを可能にする身体のサイズや色など,性を示すシグナルはその後次第に進化していった。
ではなぜ未だに同性間の性行動が行われているのか,という問いへの答えとしては,おそらく同性間の行為が進化的なコストとして考えられているより大きくないことではないか,と研究者らは考える。実際,異性間の性行為も,行為の受け入れ拒否や,生まれた子供が繁殖可能な年齢まで育たず死んでしまうことなどを考慮すると,そこまで効率は良くないため,総合的に見れば同性愛行為が目立ってコストの大きいものとはならないと考えられる。
これらの議論は現時点では仮説にすぎず,観測的な証拠を欠いているが,十分合理的なものと思われる。この研究に触発され,新たに示された視点からの議論がより深く掘り下げられることが期待される。
参考:
- https://www.nytimes.com/2019/11/26/science/same-sex-behavior-animals.html
- https://www.livescience.com/same-sex-behavior-is-old.html
性
セクシュアルマイノリティ
性行為
動物行動学
生物進化
生殖