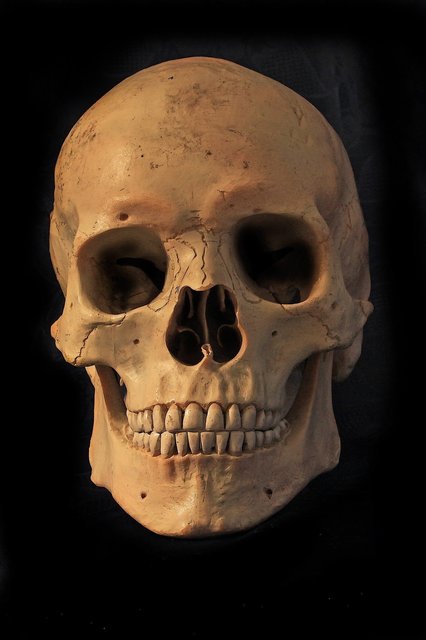30万年前の地球には,9種のヒトが生息していた。だが,現在生息しているヒトは,ホモ・サピエンスだけである。
その理由について, 古生物学者ニック・ロングリッチはThe Conversationの記事でこう説明している。
我々は類を見ないほど危険な種である。 我々は毛におおわれたマンモスや地上のナマケモノやモアを絶滅に追い込んできた。 我々は農地のために平野や森林を破壊し,地球の土地面積の半分以上を変容させてきた。我々は地球の気候さえ変化させたが,我々が最も危険となるのは,他のヒト集団に対してである。その理由は,資源と土地を奪い合うことである。
カルタゴの戦いから植民地支配まで,人類の歴史は大規模な迫害や殺しの歴史でもある。これらを踏まえロングリッチは
言語や道具利用と同様に,大量虐殺の能力とそれに従事する傾向性は,間違いなく人類本性の内在的で本能的な一部分である。初期のホモ・サピエンスが,より縄張りを守り,より暴力的でなく,より他者に対する非寛容さが少ないものだった,すなわち,今より人間らしくなかったと考える理由はほとんど存在しない。
ともっともな指摘を行う。
楽観主義者たちは,初期の狩猟採集民としてヒトの生活を平和的なものだと脚色したがるが,フィールド研究から考古学的証拠まで,初期の文化もすでに破壊的であったことをそろって示している。
そして,他のヒトたちを絶滅に追いやった大きな要因は,協力的なハンターとして成功し,外敵の脅威を克服したホモ・サピエンスが,大きく個体数を増やしたことであるという。
その結果,資源を求めてテリトリーを拡大する必要が生じ,同じ資源を巡る他のヒトとの争いに至り,彼らをすべて抹殺してしまった。
現在の相変わらず暴力的な社会を眺めれば,この血塗られた歴史から,我々の多くは何も学んでいないことがわかる。歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリはベストセラー著書サピエンス全史でこう記している:
寛容さはサピエンスのトレードマークではない。近代や現代にも,肌の色や方言,あるいは宗教の些細な違いから,サピエンスの一集団が別の集団を根絶しにかかることが繰り返されてきた。
スティーブン・ピンカーのような楽観主義者たちは,暴力の割合は歴史的に減少していることを強調する。しかし,この種の軽薄な主張には多くの批判もある。ハラリがまず指摘するのは,我々と似ているが別の種族にある動物たちに対する暴力の拡大だ:
この見方もあまりに単純化されすぎている。我々が現代のホモ・サピエンスが成し遂げたことついて自分たちを祝福できるのは,他のあらゆる動物たちの運命を完全に無視した場合だけだ。人間たちが病や飢餓から守られることによる財産は,実験室の猿,乳牛,ベルトコンベヤーの上の鶏たちの犠牲を対価としている。過去二世紀に渡り,何百億もの動物たちが工業的搾取の対象となってきた。この残酷さは地球という惑星の歴史上前例がない。
そしてデイヴィッド・ベネターがこのことに加えるのは
暴力が減少しているといっても,減少しているのは暴力の割合だけである。現在,人々は以前よりも暴力を受けにくくなっている。しかし,苦しみや死の総量は増加している。これは,危害を与える人や,他人の手による危害に苦しむ人間の数が増えたことが主な理由である。
例え暴力の割合に注意を制限したとしても,依然としてその割合が増加する可能性もある。人間の性質を考えれば,割合の減少傾向が動かしがたいものであるとは考えられない。しかし,その懸念を脇に置いたとしても,現在の割合は,減少していると言っても無視できる値からは程遠い。
我々はせめて,ロングリッチがConversationの記事の締めに記した次の言葉についてよく考えるべきだろう:
今日,星を見上げて,我々は宇宙で唯一の存在なのだろうかと考える。ファンタジーやSFでは,我々と似ているが別の存在である他の知的生命体との遭遇はどんなものになるのだろうと思いを巡らす。かつて我々はそれを経験したのだが,その遭遇が原因で彼らはもうここにはいないということを考えると,非常に悲しく思えてくる。