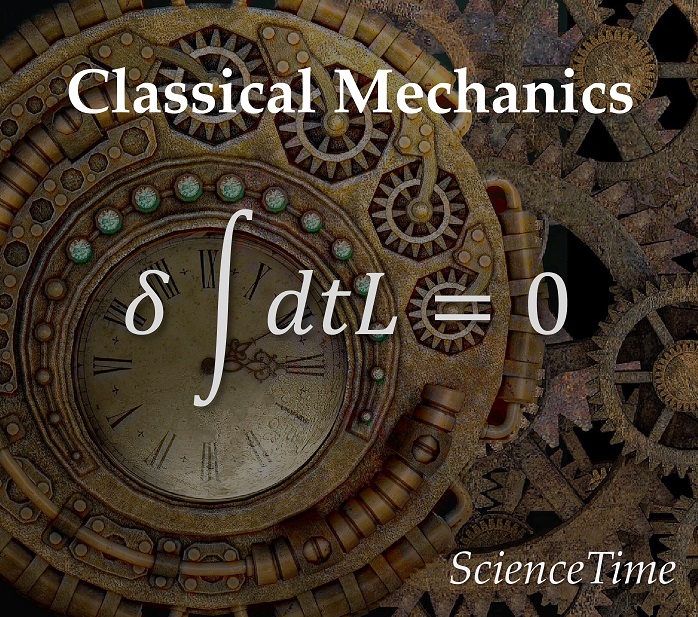正準変換
正準変数$(q,p)$から座標変換
\begin{equation}
\label{eq:canonical_transformation}
Q^i=Q^i(q,p,t),
\quad
P_i=P_i(q,p,t)
\end{equation}
を行った結果,新たなHamiltonian $H'(Q,P)$を用いても,正準方程式
\begin{equation}
\dot{Q}^i=\frac{\pd H'}{\pd P_i},
\quad
\dot{P}_i=-\frac{\pd H'}{\pd Q^i}
\end{equation}
が成り立つ場合,変換(\ref{eq:canonical_transformation})を,正準変換(canonical transformation)と呼ぶ。
正準方程式は,相空間上の作用$S$の変分が
\begin{equation}
\label{eq:delta_S_old_variables}
\delta S
=\delta \int (\sum_i p_i dq^i - H dt)
=0
\end{equation}
を満たすことと等価なのであった。
新たな変数$P,Q$が正準方程式を満たすためには,それらも同様に
\begin{equation}
\label{eq:delta_S_new_variables}
\delta S
=\delta \int (\sum_i P_i dQ^i - H' dt)
=0
\end{equation}
が成り立たなければいけない。
配位空間の場合と同様,相空間上の作用積分の被積分関数が持つ一般的任意性は,ある相空間関数$F(q,p)$の全微分$dF$を付加することである。
$F$の境界値は,相空間上の軌道の両端を固定しているという条件から
\begin{equation}
\delta \int dF
= \delta[F]_{t_1}^{t_2}
=
\sum_i\left[
\frac{\pd F}{\pd q^i}\delta q^i
+\frac{\pd F}{\pd p_i}\delta p_i
\right]
=0
\end{equation}
となり,積分に寄与しないためである。
よって,新たな変数による作用(\ref{eq:delta_S_new_variables})の被積分関数が,古い正準座標による作用(\ref{eq:delta_S_new_variables})の被積分関数と$dF$しか違わなければ,すなわち
\begin{equation}
\sum_i p_i dq^i - H dt
=
\sum_i P_i dQ^i - H' dt + dF
\end{equation}
であれば,要件は満たされる。
これを
\begin{equation}
dF
= \sum_i p_i dq^i
- \sum_i P_i dQ^i
+ (H'-H) dt
\end{equation}
と書き直すと
\begin{equation}
p_i=\frac{\pd F}{\pd q^i},
\quad
P_i=-\frac{\pd F}{\pd Q^i},
\quad
H'=H+\frac{\pd F}{\pd t}
\end{equation}
という関係が得られる。
このように,関数$F$を与えれば変換が決まるため,$F$は母関数(generating function)と呼ばれる。
母関数のLegendre変換
上の変換では,母関数が新旧の座標の関数$F=F(q,Q,t)$であると仮定した。
しかし,他の変数の組み合わせでも変換を生成できる。
$F$を
\begin{equation}
F-\sum_i \frac{\pd F}{\pd Q^i}Q^i
=F+\sum_i P_iQ^i
\end{equation}
とLegendre変換すると
\begin{equation}
\begin{split}
d(F+\sum_i P_iQ^i)
=& dF + \sum_i dP_iQ^i + \sum_i P_i dQ^i \\
%
=&\sum_i p_idq^i
+\sum_i Q^idP_i
+(H'-H)dt
\end{split}
\end{equation}
となり,新たな母関数を$F_2(q,P,t)=F+\sum_i P_iQ^i$と記せば
\begin{equation}
p_i=\frac{\pd F_2}{\pd q^i},
\quad
Q^i=\frac{\pd F_2}{\pd P_i},
\quad
H'=H+\frac{\pd F_2}{\pd t}
\end{equation}
を得る。
同様にして
\begin{equation}
F_3
\equiv
F-\sum_i \frac{\pd F}{\pd q^i}q^i
=F-\sum_i p_iq^i
\end{equation}
により,$F_3(p,Q,t)$とLegendre変換すれば
\begin{equation}
d(F-\sum_i p_iq^i)
=
-\sum_i q^i dp_i
-\sum_i P_idQ_i
+(H'-H)dt
\end{equation}
より
\begin{equation}
-P_i=\frac{\pd F_3}{\pd Q^i},
\quad
-q^i=\frac{\pd F_3}{\pd p_i},
\quad
H'=H+\frac{\pd F_3}{\pd t}
\end{equation}
を得る。
最後に
\begin{equation}
F_4
\equiv
\Phi-\sum_i \frac{\pd \Phi}{\pd q^i}q^i
=\Phi-\sum_i p_iq^i
=F-\sum_i (P_iQ^i-p_iq^i)
\end{equation}
により,$F_4(p,P,t)$にLegendre変換すれば
\begin{equation}
d(\Phi-\sum_i p_iq^i)
=
-\sum_i q^idp_i
+\sum_i Q^idP_i
+(H'-H)dt
\end{equation}
であるから
\begin{equation}
Q_i=\frac{\pd F_4}{\pd P_i},
\quad
-q^i=\frac{\pd F_4}{\pd p_i},
\quad
H'=H+\frac{\pd F_4}{\pd t}
\end{equation}
を得る。
正準変換としての運動
正準方程式に従う運動は決定論的であるから,時刻$t$における正準変数の組$q_t=q(t)$および$p_t=p(t)$を決めれば,時刻$\tau$後の値$q_{t+\tau}=q(t+\tau)$および$p_{t+\tau}=p(t+\tau)$も一意に決まる。
したがってこれらは,$q_t,p_t$の関数
\begin{equation}
q_{t+\tau}=q(q_t,p_t,\tau),
\quad
p_{t+\tau}=p(q_t,p_t,\tau)
\end{equation}
である。
したがって,運動も一種の正準変換とみなせる。
このことは,作用を軌道の始点$q_t$と終点$q_{t+\tau}$の関数$S(q_t,q_{t+\tau})$として見た場合の微分が
\begin{equation}
dS
=\sum
(
p_{t+\tau}dq_{t+\tau}
-p_{t}dq_{t}
)
\end{equation}
であり( コチラ参照),新旧の座標を変数とする母関数になっていることからも理解できる(和の添え字は省略した)。