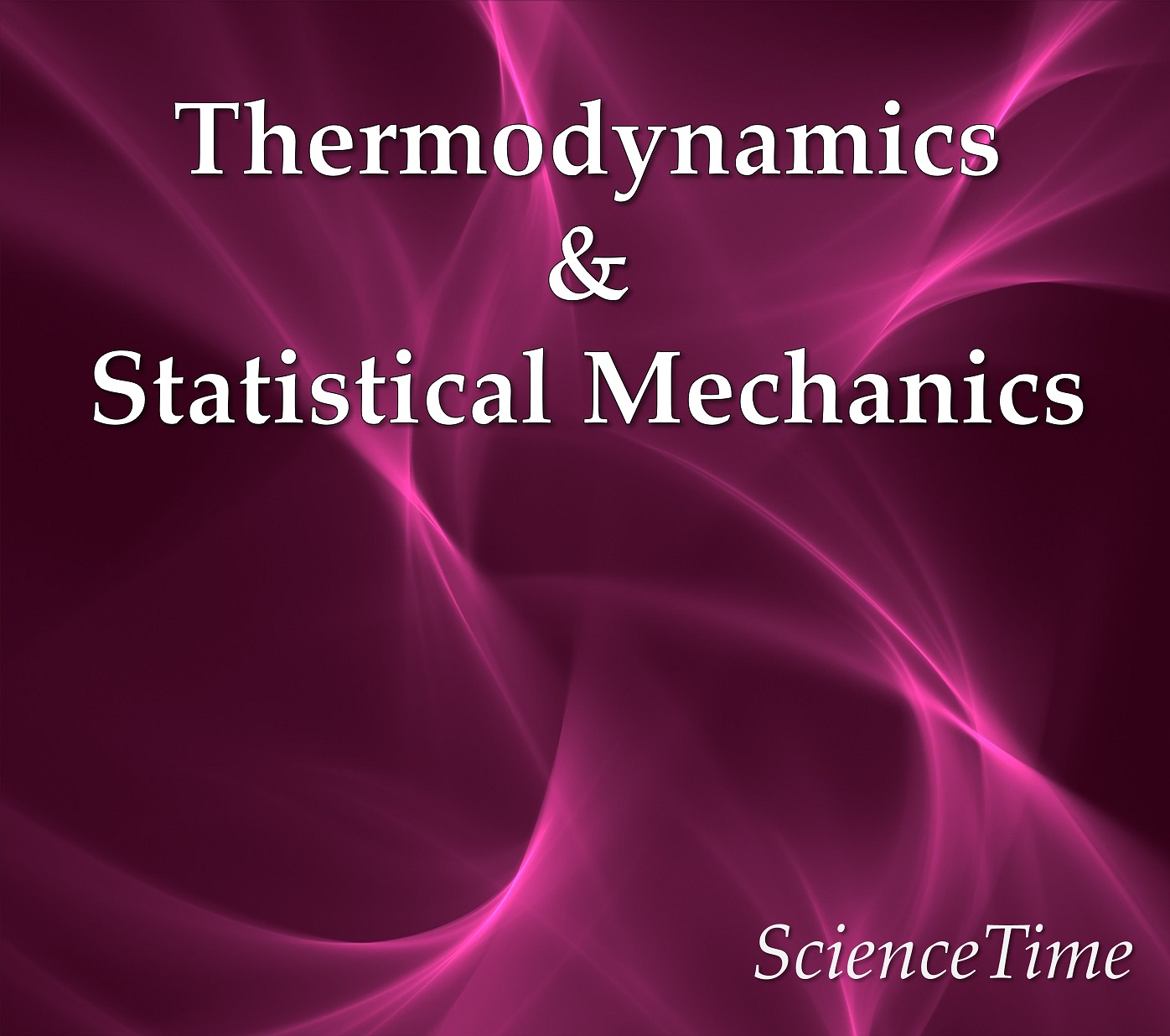Introduction
熱力学第二法則,最大仕事の原理,Helmholtz自由エネルギーについて解説する。第二種永久機関
熱を仕事に変換する装置を一般に熱機関(heat engine)というが,18世紀から19世紀半ばにかけた蒸気機関の発達により,熱機関の効率向上が物理的にも工学的にも重要な関心ごととなった。 熱機関の効率は「どのようにすれば高められるのか」,という問題を追求する過程で自然と生じるのが,効率は「どこまで高められるのか」,という疑問である。 この問いは,熱から仕事への変換に何らかの制約があるのか,あるとすればどのような制約なのか,という問いであるとも言える。
熱機関は一般に,高温の熱源から熱$Q_H$を受け取り,外に仕事$W$を行い,低温の熱源に熱$Q_L$を放出してまた元の状態に戻るというサイクルを繰り返すことで運転を続ける。 1サイクルの間にした仕事は$W=Q_H-Q_L$となり,これにより効率が
と評価される。
投入したエネルギー量以上の仕事をするような機関,すなわち第一種永久機関の実現が不可能であるという総括として熱力学第一法則が確立されたわけであるが,これだけでは無限のエネルギーリソースという夢が潰えるわけではない。 もし熱機関の効率に制限がなく,熱をすべて仕事に変えることができれば,つまり最終的に上の式で$W=Q_H$とすることが可能ならば,単一の熱源で熱機関の運転が可能になる。 例えいったん仕事に変換しきれなかった分の熱を低熱源に捨てても,それを再び回収してまた仕事に変換するという過程を繰り返せば,実質的には同じことである。
これは,熱力学第一法則に反することもなく,大気や海のような巨大な系を単一の熱源としてエネルギーをくみ出すことで,実質的にほぼ無尽蔵のエネルギーソースを手に入れられることを意味する。 あるいは低温の物体から熱をくみだして仕事に変換し,それを摩擦によって熱に変換して高温の熱源に捨てるということを繰り返せば,外部から仕事を加えることなく熱を低温の物体から高温の物体に移すこともできる。 このような理想的な機関を第二種永久機関(perpetual motion machine of the second kind)という。
熱力学第二法則
だが,この種の熱機関も実現することなく,熱機関の効率に限界があることを受け入れざるを得なかった。 このことは,熱力学第一法則とは別の法則の存在を示唆している。 熱は高温部分から低温部分に流れ,その逆が自発的に起こることはないということは経験的にもよく理解されることだが,この変化の方向性の重要性を捉え,第一法則と並べて熱力学の基本法則として明確化したのは,Rudolf Clausius(1850)であった。
この第二の基本法則,すなわち熱力学第二法則には様々な表現の仕方があり,Clausius自身もいくつかの異なる表現を用いている。 1854年の論文では
関連して同時に生じる他の変化なしに,冷たい物体から熱い物体に熱が移ることはない。
と述べられている。 また,Clausiusよりわずかに遅れて第二法則に到達したWilliam Thomson(のちのKelvin卿)は
非生物的物質の働きにより,周囲の物体の中で最も低い温度よりもさらに冷たくすることで,物質のいかなる部分からも力学的効果を生み出すことはできない。
と述べている(Thomson 1851)。 Thomsonがこう仮定した理由も,もしこの主張が誤りであった場合「海や大地を冷やすことにより,力学的効果を産出するよう自動機械を設定できてしまう」ためである。 Thomsonは非生物的なものに限定しているが,もちろん生物であってもこの制約を破ることはできない。
最大仕事の原理と自由エネルギー
Thomsonの主張は,海や大地のような単一の熱源を用いて外に正の仕事をすることはできない,ということを述べている。 ここでいう単一の熱源というのは,熱源の温度が単一かつ一定の値を取ることを意味しており,海の温かい部分と冷たい部分を利用する場合などは,単一の熱源からなる機関とはみなさない。
このThomsonの主張を念頭に,単一の熱源に接触したまま行うサイクルを考える。 これは,温度一定の環境下で行うサイクルであるから,等温過程からなる。 このようなサイクルを等温サイクルと呼ぼう。 1サイクルの間に外にした仕事を$W_{cyc}$とすると,Thomsonの主張によれば,等温サイクルでは
となる。
あるサイクルは準静的な過程から構成されていれば,それを逆行させることができる。 この逆サイクルでなされる仕事は,順サイクルでなされる仕事$W_{cyc}$と逆符号の$-W_{cyc}$である。 これが等温サイクルであるなら,Thomsonの主張は,$W_{cyc} \leq 0$かつ$-W_{cyc} \leq 0$,すなわち$W_{cyc} = 0$であることを意味している。 つまり,(\ref{eq:W_iso_cycle})で等号が成り立つのは準静的な等温サイクルの場合であることがわかる。
このように一巡すると仕事が0になるということは,あるポテンシャル関数の存在を示している(コチラを参照)。 すなわち,状態$A$から$B$に等温準静的に移る際に系がする仕事は,状態の変化の道筋によらず,ある状態関数$F=F(X)$($X$は状態変数)を用いて
と書ける。 無限小変化を考えるなら
である。 この関数$F$を,Helmholtz自由エネルギー(Helmholtz free energy)という。
(\ref{eq:maximum_work_F})はあくまで等温準静的過程でのみ成り立つ性質だということには注意しよう。 では,等温であるが準静的ではない場合はどうか。 ある等温操作で状態$A$から$B$に移り,$B$から等温準静操作で$A$に戻るサイクルを考える。 最初の操作で系が行う仕事を$W_{A\to B}^{i}$と表す。 2つ目の操作で行う仕事は,準静的操作で状態$A$から$B$に移る際の仕事$W_{A\to B}^{iqs}$の符号を逆にしたものである。 よってサイクル全体で行う仕事は
となる。 Thomsonの主張より,この値は正にはならないから
が成り立つ。 つまり,等温過程で系が行う仕事は,それが準静的過程の場合に最大になる。 状態の選択に特別な条件は課していないから,この関係は一般に成り立つ。 これを,最大仕事の原理(principle of maximum work)という。 Helmholtz自由エネルギーを用いれば
と表現できる。 これより,最大仕事の原理は次のように理解できる: 等温操作で仕事として取り出せるエネルギーには限界があり,その限界値は準静的操作を行った場合に得られ,Helmholtz自由エネルギーという状態関数の減少分に等しい。
さて,熱機関の効率に限界があるということを受け入れたならば,次の問いは,ではその限界はどこであり,何で決まるのか,ということである。 実はその限界を示す議論の骨格はClausiusやThomsonによる第二法則の確立以前に,Sadi Carnotによって与えられていた。 ClausiusやThomsonの研究も,Carnotの研究に大きな影響を受けてのものであった。 次節では,このCarnotの研究について解説する。
References
―― (2017). 生物物理学における非平衡の熱力学 (新装版). 青野修 他 訳. みすず書房.