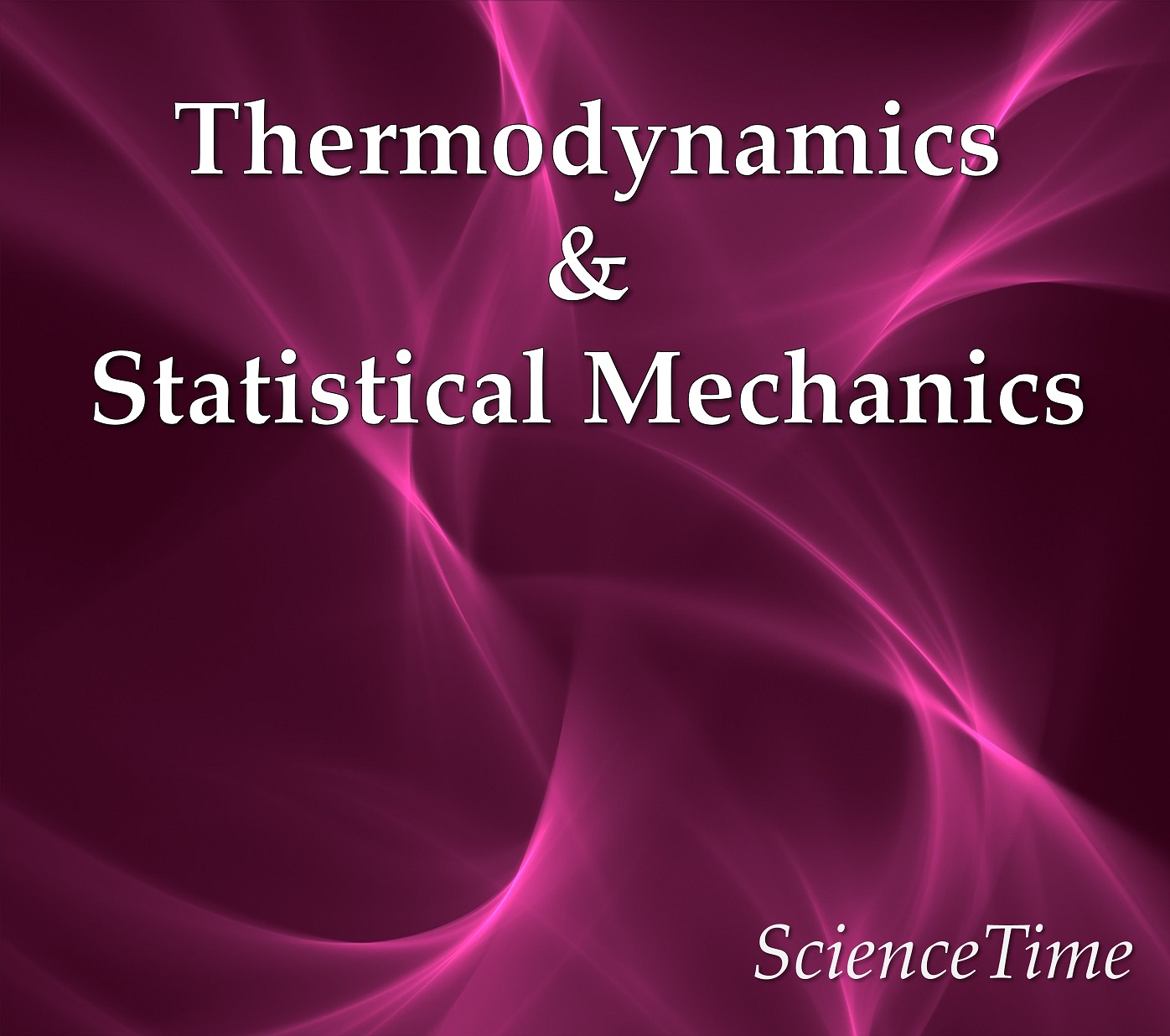Introduction
運動論の基本概念である分布関数と,その時間発展を記述する運動論的方程式の一般形を提示する。分布関数
気体を構成する分子を点粒子とみなせる場合,分子の力学的状態は,$6$次元相空間($\mu$空間)の座標$(q,p)$によって指定できる。 ここで$q=(q_1,q_2,q_3)$および$p=(p_1,p_2,p_3)$はそれぞれ一般化座標と運動量である。
回転自由度を持つ2原子分子など,より多くの自由度を持つ粒子からなる系の場合,相空間の次元はもっと大きくなる。 しかし,これらの自由度は通常無視できる。 それに関する議論は別で行うとして,以下内部自由度を持たない古典的粒子からなる系を考える。
系全体の状態は,分布関数(distribution function)によって記述できる。 $N$個の粒子からなる系の厳密な分布関数は
で与えられる。 ここで,$q,p$は相空間に張り付けられた座標(いわばEuler的な座標)であるのに対し,$q_i(t),p_i(t)$は時刻$t$における$i$番目の粒子の座標(Lagrange的な座標)である。
(\ref{eq:exact_distribution_function})を$p$全体で積分してしまえば,一般化運動量に関係なくある座標$q$にある粒子数が与えられる。 $q$を物理的空間座標$\bm{x}$にとれば
であり,これをある空間体積$\Delta V$で積分すれば,その中にある粒子数がカウントされる。
もちろん,空間全体で積分すれば,全粒子数
$N$が得られる。 したがって,(\ref{eq:particle_numer_density})は空間的な粒子数密度(particle number density)の分布を表す。
分布関数の粗視化
厳密な分布関数(\ref{eq:exact_distribution_function})は,系の力学的情報をすべて含んでおり,この時間発展を記述する方程式が解ければ,任意の時刻で系の状態を決定できる。 しかし,我々が扱う気体のような系は,$N\sim 10^{20}$個を超える膨大な粒子からなる。 ある時刻におけるすべての粒子の相空間上の位置を指定することは現実的に不可能である。 そこで,ミクロに見れば,そこに十分な粒子数を含むほど十分大きいが,マクロに見れば十分小さい相空間領域$\Delta \mu$を取り,平均操作
により粗視化(coarse-graining)する。
以下,分布関数といえば,(\ref{eq:coarse-grained_f})のようにして粗視化されたものを指すこととする。
運動論的方程式
分布関数$f(q,p,t)$は,時刻$t$に相空間上の座標$(q,p)$にある粒子の数を表している。 これらの粒子は,時間$\Delta t$後に$q+\Delta q, p+\Delta p$に移動するから,これらの粒子の分布を記述する$f(q,p,t)$は$f(q+\Delta q, p+\Delta p,t+\Delta t)$に変化する。 そして,$\Delta t\to 0$の極限で,$\Delta q\to\dot{q}dt$,$\Delta p\to\dot{p}dt$であるから
が成り立つ。
衝突が無視できる場合を考えると,各粒子は正準方程式に従って発展する。 時間発展を正準変換と考え,$q_t=q(t),p_t=p(t)$および $q_{t+dt}=q(t)+\dot{q}dt,p_{t+dt}=p(t)+\dot{p}dt$と略記すると,粒子数の保存則より
でなくてはらない。 ここで,Liouvilleの定理により
が成り立つから,$f(q_t,p_t,t)=f(q_{t+dt}, p_{t+dt},t+dt)$,すなわち
が成り立つ。 したがって,(\ref{eq:kinetic_dfdt_1})および(\ref{eq:kinetic_dfdt_2})より,無衝突系の分布関数の時間発展を記述する式が
と得られる。 これは,相空間上の軌道に沿って分布関数が一定であることを示している(これも$\mu$空間におけるLiouvilleの定理の表現の1つである)。 $q$を空間座標$\bm{x}$に取り,運動量の代わりに速度を変数に用いると
より
である。
衝突がある場合は,分布関数は運動方程式で決まる軌道に沿って一定ではないから(\ref{eq:kinetic_dfdt_2})は成り立たない。 そのため,衝突による分布関数の変化に対応する項を加えなくてはならない。 ここではそれを$(\pd f/\pd t)_{coll}$と記し
とする。 分布関数の時間発展を記述するこの一般的な式は,運動論的方程式(kinetic equation)と呼ばれる。
ここでは,衝突による分関数の変化率を表す項であることを強調するため上のような表記を採用したが,衝突項には他にも様々な表記が用いられ,同じものを$C(f)$のように記すことも多い。 以下,希薄な気体における衝突項の具体的な形を求める。
References
――(1982). 物理的運動学 (ランダウ=リフシッツ理論物理学教程) 1 & 2. 井上健男ほか訳. 東京図書.